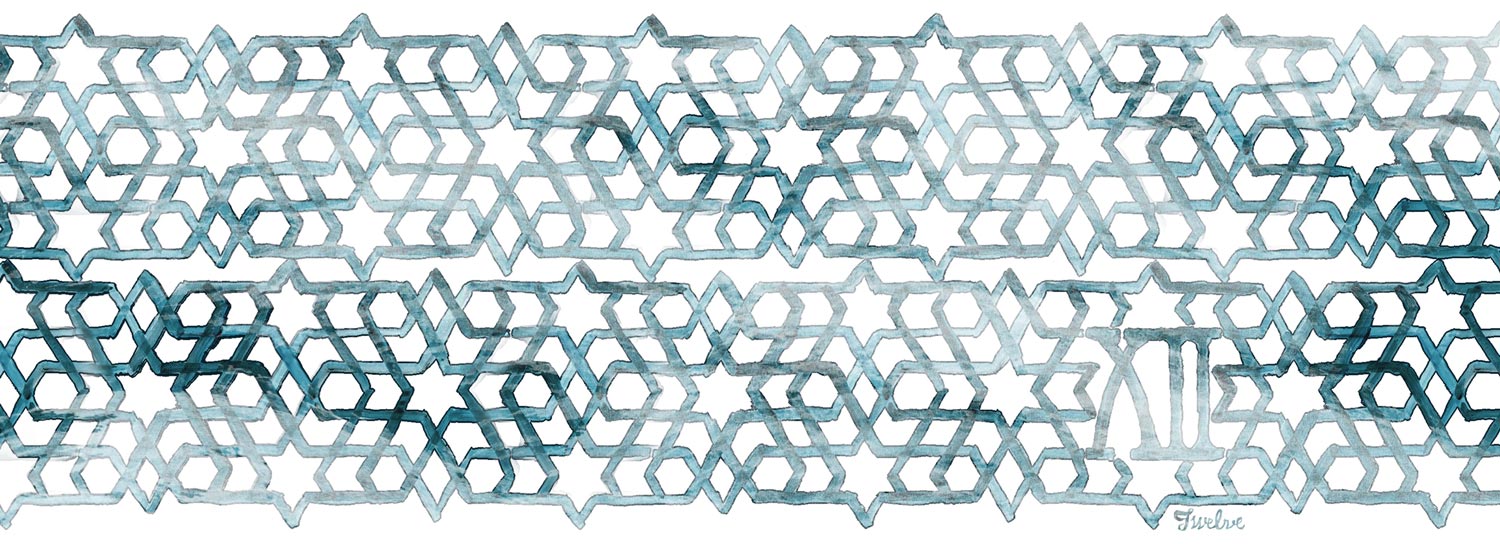.
というわけで、パキプスのベアルートを腐らせてしまったわけですが、それでもポジティブにいかなければならないので、次へ活かすためにいろいろ考えました。
.
パキプスのベアルート株は、生きようとする部分(発根した部分)と、進行していく腐りの部分がそれぞれ別に進行(それぞれが拮抗)しているんではないかと思いました。
流通しているベアルート株(葉が付いていたり、肌が緑だったりする場合、)は、生きている株と、死んでいる株が、アタリ/ハズレのように存在しているというよりは、輸入された時点で、よほど変な目にあっている株でなければ、半死にのような(一時的に休眠状態に入ろうとしている)状態なんではないかと思いました。
.
もしかしたら、少し発根した時点で、土に移せばよかったのかもと考えることもできます。
.
そもそも水耕栽培は必要だったのかとか。
.
下の写真のように、ベアルートの株を水耕栽培のために水に浸すと、パキプスから樹液が出て、水が茶色っぽくなります。
.

植物の樹液は、人間でいえば血液のようなもので、当たり前ですが、その植物にとってとても重要なものです。
外から侵入してくる細菌などの外敵をブロックしたりするなどの免疫力も持っているはずです。
.
パキプスはウルシ科なので、ウルシといえば強力な樹液を持っているイメージもあります。
それがこんなに大量に流出しまうのは、果たして正解なのかわかりません。
.
水耕栽培を否定するようなことではありませんが、土の三相分布のように、固相、液相、気相のバランスを作るためにも、土に植えるのは、やはり意味があるのかもしれません。水耕だと液相が100%ということになりますよね。
.
今回のことを踏まえて、今後は、水耕で何日も水につけるというのは避けて、オキシベロンなどの発根剤の溶液に数時間、漬け置く程度にして、あとはCLONEXなどの発根ジェルを塗って、軽めで無菌の用土に植えることにします。
.
なんだか振り出しに戻る感じです。
ベアルートからの発根管理はリスクも高いですが、活着している株を購入するよりも、安く買える場合がほとんどですし、何よりもとても楽しいです。
.
実生に楽しみを見出す人もいれば、ベアルートの株にチャレンジするのが楽しい人もいれば、または完成したようなかっこいい鉢に植えられた作られた株を買うのがいいという人もいると思いますし、楽しみ方はそれぞれですね。
.
今回は残念な内容ですが、失敗ばかりではないので、次回は成功の方をおしらせします。
.
twelve 青木 健太朗
.
.
関連記事